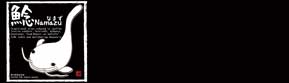
みなさんは「ナマズ」と聞いて、まずどのような姿を思い浮かべますか。
おそらく多くの方々が連想するのは、平らな頭に長い口ひげ、つぶらな瞳にやや受け口の口元、そしてヌルヌルとした表皮だと思います。
そんな見た目はどこか愛らしいナマズですが、日本では古くから「土の中のナマズが暴れると地震が起こる」という言い伝えがあり、強い存在として人々の価値観に影響を与えてきました。しかし、ナマズはもともと川や池などに広く生息する淡水魚。なぜ地震と結びついたのでしょうか。また、ナマズにまつわる昔話をみていくと、そのイメージには様々な違いがあることがわかります。たとえば、ナマズが通行人を飲み込む“怪物”として恐れられている地域もあれば、溺れた子供を背中に乗せて助ける“救世主”や”守り神”として語られることもあります。
私はこれまで、書籍、古書、論考、市誌、村史、郷土史、手記などの400を超える関係資料を手がかりに、200箇所以上のナマズにまつわる
伝承地を訪れました。その中で明らかになったことは、多くの伝承が地震よりも洪水や旱ばつによる雨乞いと深く結びついているということでした。
一方で、西日本の地域では、”皮膚病”との結びつきが広く浸透している---つまり、ナマズのイメージは、地域によって実際には異なる捉え方をされているのです。
ナマズにまつわる伝承地は、北海道、沖縄を除く、5つの地方に分類されます。
⑴ 九州地方(熊本県 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 宮崎県 鹿児島県)
⑵ 中国・四国地方(岡山県 広島県 島根県 鳥取県 山口県・徳島県 香川県 高知県 愛媛県)
⑶ 近畿地方(滋賀県 三重県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 大阪府)
⑷ 中部・北陸地方(岐阜県 愛知県 静岡県・富山県 石川県 福井県 長野県)
⑸ 関東地方(東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 栃木県 茨城県 群馬県)
⑹ 東北地方(宮城県 福島県 岩手県 秋田県 青森県 山形県)
このホームページでは、全国各地に伝わるナマズに関する伝承や文化を、昔話・絵馬・祭・兜・要石・信仰・食文化・鯰絵(なまずえ)などを通して、さまざまなテーマから取り上げています。
かつて人々は「ナマズ」という存在を通して、何を伝えようとしていたのでしょうか。あなたの住む地域にも、ナマズにまつわる伝承が残っているかもしれません。ぜひ探してみてください。
2024年5月
鯰の民俗文化会 代表 細田博子
「地方別・ナマズ伝承地位置図」は、2016年から開始した調査結果をもとに作成したものです。
本図では「地震と言えばなぜナマズなのか」という疑問を明らかにするため活断層の名称も示していますが、
地震との相関性を裏付けているものではありません。
実際の地域ごとの伝承を調べると、ナマズの話が川や沼とも密接に関係していることが見えてきます。
本サイトでは、ナマズの多様な側面を明らかにしていきたいと考えています。
現在も継続中のフィールドワークの成果は、随時更新しております。
本図の使用につきましてはご遠慮くださるようお願い申し上げます。
本HPで掲載している画像や文章等につきまして、著作権法に基づき、無断使用、転載、改変使用を禁止致します。